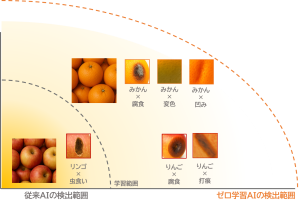多品種少量生産とは何か?日本の製造業が抱える構造的課題と、その解決のヒント
多品種少量生産の現状と課題
解決策は変動に強い生産方式と新技術の融合
この記事でわかること
日本の製造業では、近年「少量多品種生産」というキーワードが頻繁に語られるようになっています。なぜこのような生産形態が注目されているのか、どのような背景があるのか、そしてそれにどう対応すべきなのか。この記事では、製造現場の構造的課題と向き合いながら、少量多品種生産の実態と対応策、そして技術導入の際に陥りがちな“手段の目的化”について解説します。
なぜ少量多品種生産が増えているのか?
- 顧客ニーズの多様化: 消費者は「大量に同じもの」ではなく、「自分に合ったもの」を求めるように変化しました。
- グローバル生産体制への移行: 生産管理のリソースが相対的に少なく済む大量生産はコスト面で有利な海外拠点へ移管され、海外では効率的な生産が難しい小ロット・高付加価値製品が国内では中心になりつつあります。
- 中小企業の特性: 少人数・高い柔軟性を備えた中小企業では、顧客ごとの仕様変更や多品種対応に強みを持つケースが多く、結果的に少量多品種の案件を担う割合が高くなっています。
- 国内拠点のマザープラント戦略: 生産技術の開発や製品立上げ期の製品を作り込み場所として国内拠点を活用し、そのノウハウを海外生産拠点へ展開する動きも増えています。
多品種少量生産の定量的な比率と今後の方向性
日本の製造業では、特に中小企業層を中心に「少量多品種」が事実上のスタンダードになりつつあることが、複数の調査から明らかになっています。
全国中小製造業調査
独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)が全国の中小製造業1,000社超を対象に実施した調査によれば:
- 「多品種少量生産中心」と回答した企業:478社
- 「量産中心」と回答した企業:225社
→ 全体の約6割が“多品種少量中心”の生産体制であると回答しており、その比率は量産中心の企業の2倍以上にのぼります。
【出典:JILPT『中小企業における人材育成・技術承継に関する実態調査報告書』(2013)】
北九州地域の中小企業調査
北九州市立大学が北九州地域の中小製造業向けに実施した調査では、以下のような傾向が見られました:
- 自社売上に占める少量多品種製品の比率が「71%以上」と回答した企業:40.0%
- 同比率が「30%以下」とした企業:34.6%
→ 地域レベルでも、多くの企業において少量多品種生産が売上の中核を占めていることが確認されます。
【出典:北九州市立大学 リポジトリ『地域中小企業における多品種少量生産の現状分析』(2017)】
政策的な位置づけ
経済産業省が発行する「ものづくり白書(令和元年版ほか)」でも、こうした少量多品種型への対応力が日本の製造業の生き残りに不可欠であると明記されています。
顧客ごとの仕様変更や高付加価値製品への転換が求められる中、柔軟な生産体制の構築と、それを支える技術や人材の確保が今後の課題とされています。
【出典:経済産業省『ものづくり白書』(meti.go.jp)】
このように、「少量多品種」はもはや一部の特殊な生産形態ではなく、日本の製造業全体の主流のひとつとなっていると言ってよいでしょう。とくに中小製造業においては、「受注対応の多様化」や「取引先要求への即応」など、実務的な観点から自然と多品種対応へシフトしている現状があります。
多品種少量生産を支える生産方式
多品種少量生産は、段取り時間の増加、品質の安定性維持、人材の多能工化など多くの課題をはらんでいます。そこで多品種少量生産への対応方法として、以下の2つの方式について日本国内で実際に採用している企業の具体例を紹介します。それぞれの企業名、製品カテゴリ、方式採用の背景・狙い、得られた効果に注目します。
1. 複数品種を1ラインで連続生産する多種混流生産の採用事例
多種混流生産は、1本の生産ラインで複数種類の製品を連続して生産する方式です。日本の製造業では、自動車産業を中心に以下のような事例があります。
- トヨタ自動車|動力源・車種の混流対応(自動車)
トヨタの元町工場では、セダン、SUV、ミニバン、そしてガソリン車・HEV・BEV・FCEVといった多様な車種を1ラインで混流生産。柔軟性と設備稼働率の両立を実現しています。 - マツダ|計画順序生産による高頻度混流(自動車)
顧客注文に応じて1台単位で組立順序を管理し、部品サプライヤーとも連動することで短納期高精度の生産を実現。1960年代から混流に取り組む先駆者。 - キヤノン株式会社|共通ライン設計による混流生産(事務機器)
ONEラインと呼ばれる共通組立ラインで段取り時間を60秒以内に短縮。設備・治具を共通化し、多品種並行生産を実現。生産性4.3倍に向上。
2. セル生産方式の採用事例
セル生産方式は、1人または少人数の作業者チームが製品の複数工程を受け持ち、完成まで組み立てる生産方式です。多品種少量生産への対応力や作業者の技能活用と育成の面から、多くの日本企業が導入しています。具体例として次のようなケースがあります。
- カシオ計算機(デジタルカメラ・腕時計)
ダイナミックセル生産方式を採用。作業者1人が複数工程を担う仕組みで、在庫削減・短納期対応・柔軟なライン再編を実現。 - ソニーGMO・湖西サイト(プロ用映像機器)
月に100種類もの製品を生産する超多品種ライン。作業ガイド「E-Assy」などを導入し、品質と生産性を両立。 - 京セラ(電子部品)
モジュール化設備による生産性向上と人材育成による多能工化で、段取り替えの時間短縮と柔軟なレイアウト変更を実現。
以上、多種混流生産とセル生産方式について、日本国内企業の事例を紹介しました。それぞれの方式は、多品種少量生産時代において生産性・柔軟性・人材活用を高める有効なアプローチであり、生産数量や品種数、現場の実態に応じて採用・最適化されています。
多品種少量生産を支える技術
多品種少量生産を支える要素技術は、大きく「作らない時間の削減」「効率的な生産の支援」「属人化の排除」の3つの観点で整理できます。
| 観点 | 解決したい課題 | 具体的な技術例 |
|---|---|---|
| 作らない時間の削減 | 段取り・調整・計画待ちといった“非稼働時間”の短縮 |
など |
| 効率的な生産の支援 | 少人数・短納期でも安定した品質と生産性を確保 |
など |
| 属人化の排除 | 特定の人にしかできない作業や判断を減らす |
など |
これらの技術は日進月歩であり、定期的な選定と見直しが重要です。特に昨今は生成AIの影響が大きく、従来は技術的に難しかった領域にも対応可能な技術が登場しています。最新技術がもたらす選択肢の広がりを前提に、自社にとって本当に必要な技術は何かを見極める視点がますます重要になっています。
手段の目的化に気をつける
よくあるのが「見える化」のためのダッシュボードや、「AI活用」のためのAI外観検査システムの導入など、技術導入そのものが目的になってしまうケースです。
これを避けるには、QDC(Quality/Delivery/Cost)のどれを改善したいのかを明確にし、理想と現状のギャップを把握したうえで、それを埋める技術が何かを考えることが重要です。
おわりに
少量多品種は、日本の製造業において避けられない現実です。対応には方式の工夫、技術の活用、そして“目的を見失わないマネジメント”が不可欠です。
技術はあくまで道具。目的を明確にし、それに合った技術を必要最小限で導入する。そんなバランス感覚が、現場の強さをつくっていくはずです。